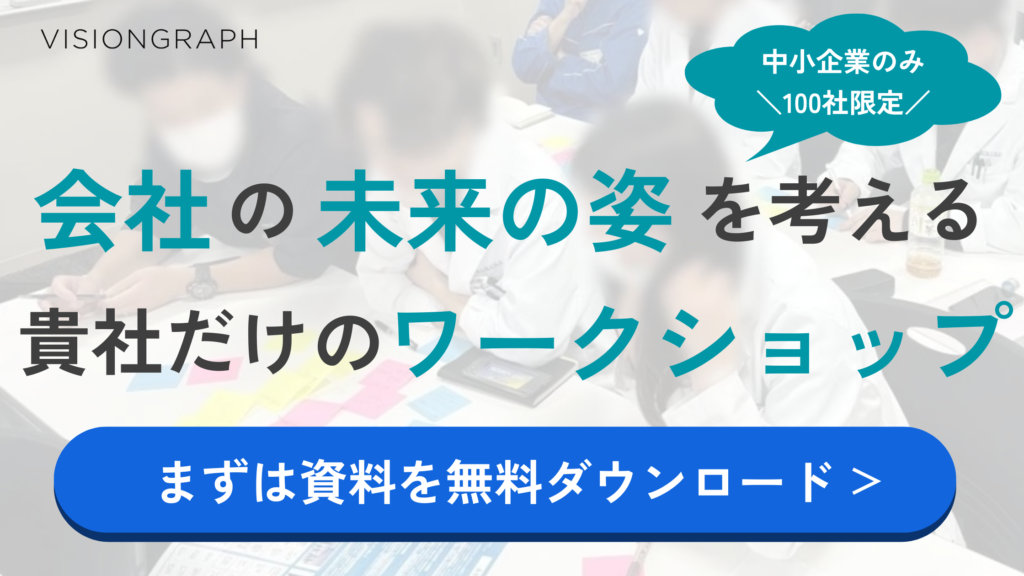近年「中期経営計画を、やめました」と宣言する大手企業が相次いでいます。
味の素、伊藤忠商事、キリンホールディングスなど、多くの企業が従来の3〜5年スパンの中期経営計画を廃止または見直し、より柔軟で実効性のある経営スタイルへと移行しつつあります。
背景にあるのは、変化のスピードが加速する現代において、固定化された数値目標や形式的な計画がかえって現場の機動力を損ねてしまうという問題です。では、中期経営計画をやめた企業は、その後どう経営をマネジメントしているのでしょうか?
本記事では、中期経営計画を廃止する動きの背景と、代替となる開示・管理手法、そして中期経営計画を再定義するためのヒントを事例とともに解説します。

中期経営計画を廃止する企業が増えている背景とは?
かつては企業の“羅針盤”として定着していた中期経営計画が、今まさに転換点を迎えています。
大手企業が相次いで「中期経営計画廃止」や「再定義」に踏み切っているのはなぜか。その背景には、単なる流行では済まされない構造的な変化が存在します。
経営環境の不確実性と計画の賞味期限の短さ
現在の経営環境は、従来とは比べものにならないほど流動的です。地政学的リスク、気候変動、為替・金利の急変、AI・DXの技術革新など、企業を取り巻く前提条件が半年〜1年単位で変化していく時代において、3〜5年という固定スパンの計画は、その“賞味期限”が極端に短くなっています。
たとえば、2020年のコロナ禍を契機に、多くの企業が中期経営計画を途中で修正または停止する事態に直面しました。環境変化に合わせて柔軟に戦略を変えられない状態は、むしろ経営の硬直性を助長するリスク要因となり、中期経営計画の有効性そのものが問われるようになったのです。
経営資源の配分や事業選択を「今ある情報」だけで数年分固定してしまうことのリスクに、経営者自身がようやく危機感を持ち始めたとも言えるでしょう。
数値偏重による現場の硬直化
多くの中期経営計画は、売上目標やROE、営業利益率といった財務KPIを軸に構成されます。しかし、その数値が“トップダウンで割り振られた目標”として各現場に落ちることで、戦略が「管理のための帳尻合わせ」にすり替わってしまう現象が起こっています。
たとえば味の素では、過去の中期経営計画で設定された利益目標が、現場に「守るべきノルマ」として作用し、挑戦的な投資や変革を抑制する結果になっていたと自己分析しています。「数値目標を掲げることで動きづらくなる」という逆説的な状態に、組織全体が自覚的になったのです。
また、数値の達成そのものが目的化されることで、たとえばESG施策のような“短期では測れない価値”が軽視される傾向も生まれます。これにより、企業の長期的な競争力が削がれる可能性すらあるのです。
参考:味の素株式会社「中期ASV経営 2030ロードマップ」
四半期決算・ESG開示の常態化
かつては3年スパンの中期経営計画が、企業の将来像を説明する主要なツールでした。しかし現在では、四半期決算・統合報告・ESGレポートなど、情報開示の頻度と内容が高度化しています。これは投資家との対話をより“リアルタイム”で行うことが求められる時代になったということでもあります。
たとえば、伊藤忠商事は中期経営計画を廃止したうえで、毎期の利益計画と長期ビジョンを組み合わせる形で経営の方向性を開示しています。これにより、数字だけでなく経営者の意図や戦略の柔軟性まで含めた“動的な説明”が可能になります。
また、ESG指標などの非財務KPIを重視する機運が高まっており、年単位の変化しか追えない中期経営計画の開示様式では、企業の変化を説明しきれなくなっている現実も背景にあります。
参考:伊藤忠商事株式会社「2025年度 経営計画説明資料」
海外投資家との認識ギャップと脱・形式主義
海外の機関投資家やアナリストは、企業との対話において「柔軟な戦略更新」や「経営者の本音・姿勢」を重視する傾向があります。彼らにとって、定型的な中期経営計画はむしろ“フォーマットに沿った作文”にしか映らず、現実の経営との乖離を感じさせる要因となりがちです。
味の素は中期経営計画廃止に際し、「投資家との信頼関係は定期開示よりも継続的な対話で築くべき」と明言しています。これは日本企業の“年中行事”としての中期経営計画策定が、むしろグローバルスタンダードから逸脱していることの表れでもあります。
企業価値の評価軸が「長期的な変革力」や「パーパスに基づく意思決定」にシフトしつつある今、固定型の中期経営計画ではこうした期待に応えられない。そう判断した企業が、“脱・形式主義”の姿勢を打ち出すようになったのです。
参考:味の素株式会社「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」
実際に中期経営計画を廃止した企業の事例
中期経営計画の形式的な運用を見直す企業は増えています。ここでは、味の素、伊藤忠商事、キリンホールディングスの3つを事例として紹介します。
味の素:ASV経営と“進化型経営”への転換
味の素は2023年、「中期経営計画」を明確に廃止し、代わりに「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)」と「2030ロードマップ」に基づく“進化型経営”への転換を発表しました。これは、従来の3~5年スパンでの数値目標管理から脱却し、「常に変化し続ける経営」の実現を目指すものです。
背景にあるのは、変化の激しい事業環境への対応と、社会価値・経済価値を両立する経営の実践です。たとえば、同社は2030年に向けて、売上・利益といった財務KPIに加え、「健康寿命延伸への貢献人口」「CO₂排出削減量」といった非財務KPIを重視。これらを“経営の現在地”として定点観測しつつ、柔軟に戦略を修正する体制へ移行しています 。
また、資料内では、従来のPDCA型経営から、「実行と検証を同時並行で進める“進化型”のマネジメント」への変化が明示されています。つまり、年1回の計画更新を前提とする中期経営計画は、同社にとってもはや意思決定のスピードや変化対応力を阻害する存在だったのです。
さらに投資家向けにも、単年度・中期・長期のKPIを一元的に提示する「KPIカタログ」を策定することで、中長期ビジョンと実行の連動性を可視化。これにより形式主義的な中期経営計画開示から脱却し、真の対話型IR(Investor Relations)へと転換しています 。
このように、味の素の事例は、経営管理の“型”そのものをアップデートし、不確実性の時代に対応する先進企業の姿を象徴しています。
参考:味の素株式会社「中期ASV経営 2030ロードマップ」
伊藤忠商事:中期経営計画を廃止して単年度の方針公表に切り替え
伊藤忠商事では、2024年4月に「中期経営計画」を廃止し、より確実性の高い「単年度の経営計画」を毎期公表する方針へと転換しました。
この背景には、中長期的な経営の羅針盤として策定された経営方針「The Brand-new Deal」の存在があり、これに基づいた持続的な企業価値の向上を目指す姿勢が見受けられます。
中期経営計画という「3年間の枠組み」に縛られず、長期ビジョンと単年度の確実な積み上げを組み合わせることで、かえって組織の実行力と柔軟性が高まった事例と言えるでしょう。
参考:伊藤忠商事株式会社「2025年度 経営計画説明資料」
キリンホールディングス:固定式の中期経営計画を廃止し「ローリング方式」へ移行
キリンホールディングスは、従来の3年間固定の中期経営計画を実質的に廃止し、柔軟性を高める新しい運用方式へと移行しました。これにより、もはや「固定された3年スパンの計画」をそのまま使い続けるのではなく、環境変化に応じて計画自体を毎年見直す仕組みに変更しています。
固定式中期経営計画が機能しづらくなった主な要因として、以下のような事例が挙げられています。
- ウクライナ侵攻による国際情勢の急変やそれに伴うインフレ
- ミャンマーでの政治リスクの顕在化とグループ事業への影響
- 為替・原材料価格など、策定当初には想定しづらい外部要因の連続
実際に、2022年時点で策定した3カ年計画におけるROIC(投下資本利益率)目標は、こうした変化の影響を受けて達成が困難となったとされています。こうした事態を受け、計画の柔軟性を高める必要性が強まったのです。
参考:キリンホールディングス「長期経営構想キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」
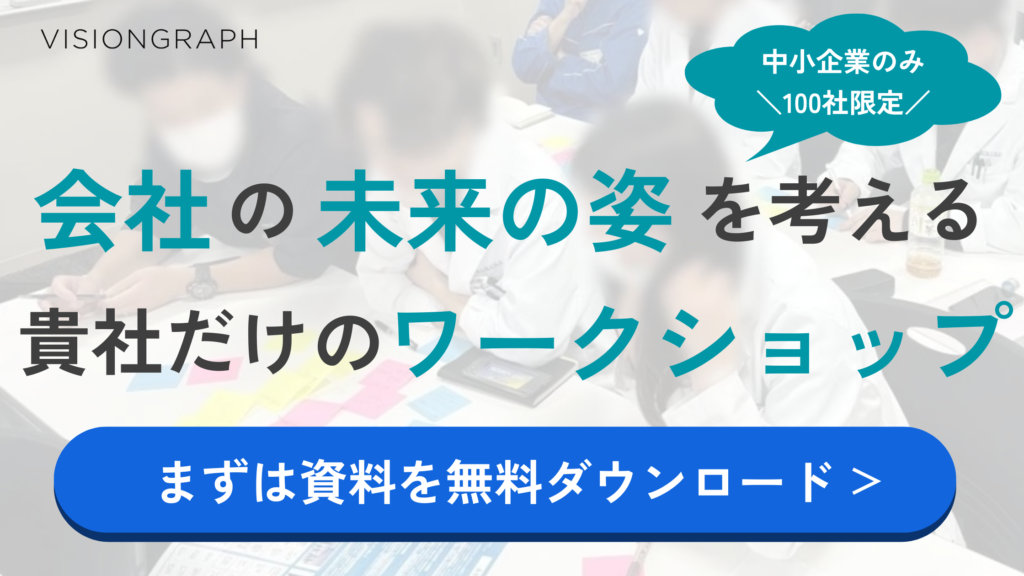
廃止=無計画ではない。新しい経営管理スタイルとは?
中期経営計画を廃止した企業が増えているからといって、経営が場当たり的になっているわけではありません。むしろ従来の硬直的な計画策定から脱却し、「変化への適応力」を高めるための新しい経営管理スタイルへと進化しているのが実情です。
こうした新潮流では、単年ベースのガイダンスや、柔軟な目標運用、ステークホルダーとの継続的な対話など、従来の「計画」よりも“運用のあり方”に軸足を置いたアプローチが重視されています。
単年ガイダンス+経営方針のハイブリッド型
従来の3〜5年単位の中期経営計画ではなく、年度単位での利益目標やガイダンスと、中長期的な経営方針・ビジョンを併存させる「ハイブリッド型」が注目されています。
この手法では、「短期の実行力」と「中長期の方向性」を分けて設計し、数値に縛られすぎず柔軟な判断が可能となります。市場環境が変化した際も、経営方針を保ちつつ具体的施策を調整しやすく、実行と説明責任のバランスが取りやすいのが特徴です。
長期ビジョン×柔軟KPI運用のレンジ型管理
将来の不確実性に対応するため、KPIの設定も「一点予測」ではなく、レンジ(幅)での目標管理が進んでいます。
例えば「利益成長率3〜7%」のように、ある程度の許容幅を持たせたKPIを設定することで、意思決定の柔軟性が高まり、事後的な説明責任も果たしやすくなります。また、KPIは年次で見直され、戦略との整合性や現場の納得感も重視される傾向にあります。
ステークホルダーに対する「動的な説明責任」の強化
中期経営計画が果たしていた「投資家向けの説明責任」機能は、新しい形に再設計されています。ポイントは、**“静的な計画”ではなく“動的な方針と実行のレビュー”**に移行していることです。
定期的な経営方針の再説明、KPIのアップデート、ESGや人的資本といった非財務領域の開示強化などにより、単なる数値の進捗報告ではなく、「なぜこの施策を行うのか」「どう状況が変わったのか」を説明する姿勢が重視されています。
中期経営計画から“対話と検証”型の経営へ
最大の変化は、「計画通りに進めること」よりも「変化に対応し、対話を通じて軌道修正すること」に価値が置かれるようになった点です。
組織内でも、トップダウンの達成主義から、現場との対話を重視する「検証とフィードバック」の経営へとシフトが進んでいます。これにより、経営陣と現場が戦略の意味を共有し、実行の質を高めていくプロセスそのものが、企業価値向上の源泉とみなされています。

中期経営計画を再構築する際の視点と代替フレームワーク
従来の中期経営計画(いわゆる「中期経営計画」)は、3〜5年の固定的な数値目標を掲げ、社内外へのコミットメントを明確にする手段でした。しかし、変化の激しい経営環境においては、柔軟性や適応力に欠けるとの課題が指摘されています。そこで近年は、「中期経営計画そのものの再定義」や「代替的な経営管理スタイル」への転換が模索されています。
以下では、実務的に中期経営計画を見直す際の視点と、その代替となり得るフレームワークについて紹介します。
「積み上げ」×「逆算」のハイブリッド設計(表あり)
経営計画の設計においては、「現場主導で積み上げた実行計画」だけでなく、「ありたい未来から逆算した挑戦的ゴール」の両方を意識する必要があります。これらを統合したハイブリッド型の計画設計が近年注目されています。
| 設計視点 | 主体 | 特徴 | 課題 |
| 積み上げ型 | 各部門・現場 | 実現可能性が高く着実 | 保守的になりやすい |
| 逆算型 | 経営層・戦略部門 | ビジョンドリブンで挑戦的 | 実行性が不透明になりやすい |
| ハイブリッド型 | 経営+現場協働 | 現実性と挑戦性のバランス | 協働設計に時間がかかる |
現場の納得感と経営の戦略性を両立させるためには、対話のプロセスを重視した設計が不可欠です。
OKRやアジャイル経営との統合(V2MOM等)
中期経営計画の代替フレームワークとして、OKR(Objectives and Key Results)やアジャイル経営、さらにはセールスフォースが採用するV2MOM(Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures)などが活用されています。
これらは固定された数値目標ではなく、ビジョン達成に向けた「行動の一貫性」と「短期的な軌道修正」を可能にする仕組みです。以下に比較を示します。
| フレームワーク | 特徴 | 中期経営計画との違い |
| OKR | 定性・定量目標の組合せ、定期見直し | 目標設定が柔軟かつチャレンジング |
| アジャイル経営 | スプリント形式の短期実行+振り返り | 毎四半期単位で戦略を見直せる |
| V2MOM | ビジョンと手段、課題を明示 | 意思決定の透明性を高める |
これらを中期経営計画の構造の中に部分的に組み込むことも実務的な選択肢です。
こうした代替フレームワークを検討する際、共通して問われるのが「自社は、どんな未来を目指しているのか」という点です。
数値や経営ビジョンの前に、まず必要なのは、経営陣だけでなく社員一人ひとりが共有できる“未来の方向性”です。
近年では、この未来像をトップダウンで決めるのではなく、社員との対話を通じて言語化する「未来洞察」を行う会社もでてきています。
未来像を起点にすることで、OKRやKPI、単年度計画も単なる管理指標ではなく、「なぜそれに取り組むのか」を支える意味のある道具へと変わっていきます。
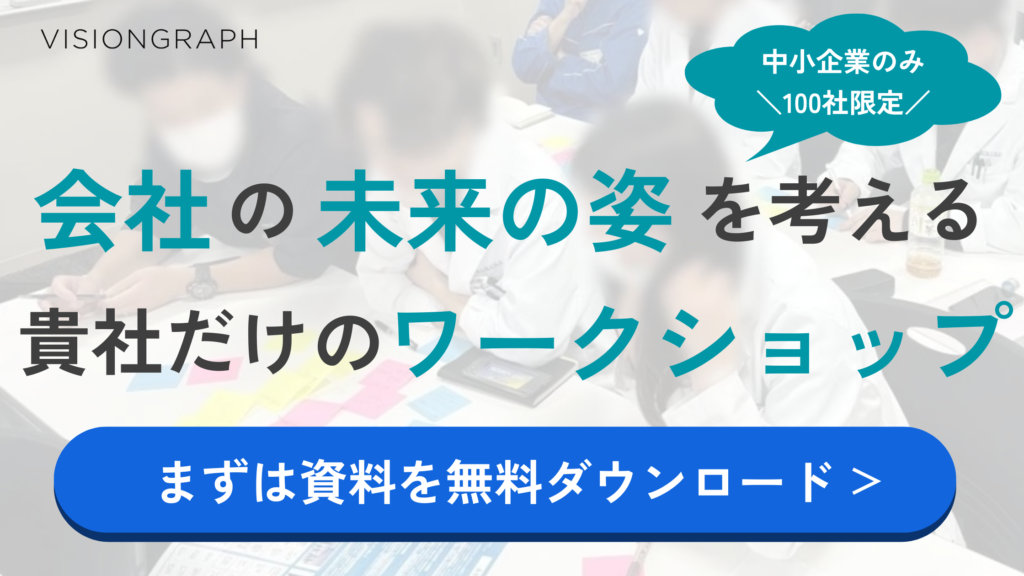
数値よりも「問い」と「仮説検証」を中心に据える
従来型の中期経営計画では、「売上◯億円」「利益率◯%」といった数値目標が重視されがちでしたが、変化が激しい環境下ではその実効性が疑問視されています。むしろ「どんな未来をつくりたいのか」「なぜ今これに挑むのか」といった“問い”を起点にした仮説思考が求められます。
こうした「問いの言語化」と「検証サイクルの内製化」は、経営の思考を可視化し、従業員の納得感や自律性の醸成にもつながります。
- 例:「Z世代の定着率をどう上げるか?」→仮説→打ち手→振り返り→再仮説
- 例:「気候変動への対応が自社にどのような機会/リスクをもたらすか?」
数字よりも“意味のある問い”を投げかけ、それを全社で検証していく姿勢が、中期的な経営の軸になります。
こうした問いを組織の中で機能させるためには、経営の言葉をいきなり「計画書」に落とすのではなく、「未来の会社案内」のような社員が参加しやすい形からはじめてみるのも良いでしょう。
社員とともに未来像を描き、それを共有言語として持つことで、仮説検証や意思決定が“自分ごと”として回り始めます。中期経営計画を支える土台として、こうした未来ビジョンの共創プロセスが注目されているのです。
社内向けと社外向けでメッセージを分ける設計
中期経営計画は本来、社内外の多様なステークホルダーとの対話の道具ですが、「一枚岩の資料」で伝えようとすると、誰にも響かない形式的な文書になりがちです。
そのため、社内向けと社外向けでメッセージを分ける設計が有効です。
- 社内向け:現場がアクションにつなげやすい内容・問い・検証方法
- 社外向け:株主・顧客・パートナーに対する意図と信頼性を示す方針
特に人的資本経営やESGが注目される現在、非財務情報の表現や「ストーリー性」も重要となっています。単なる「目標値」ではなく、「どこを目指し、なぜそう考えているか」の解像度を高める必要があります。
まとめ:中期経営計画の「終わり」ではなく「進化」をどう描くか
中期経営計画の見直しや廃止は、決して「無計画」や「方針の喪失」を意味するものではありません。むしろ、変化のスピードが増す現代において、従来の“静的な3〜5年計画”では組織を柔軟かつ機動的に動かすことが難しくなってきています。
そこで注目されているのが、単年度ガイダンスと長期ビジョンを組み合わせたハイブリッド型、KPIを「目標」ではなく「探索の出発点」とするレンジ型の運用、さらにはOKRやアジャイルマネジメントとの統合といった新しい経営管理スタイルです。これらに共通する前提として、「どんな未来を目指しているのか」という方向性が、組織の中で共有されていることが欠かせません。
重要なのは、「計画を立てること」ではなく、「仮説をもとに動き、対話を重ねながら検証すること」。中期経営計画を“発表して終わり”ではなく、“変化を前提とした経営のダイアログの場”として捉えることで、ステークホルダーとの信頼構築や企業価値向上にもつながります。
その土台となるのが、経営陣だけで描かれたビジョンではなく、社員と共に言語化し、共有された「未来の会社像」です。
中期経営計画を「終わらせる」かどうかが問題ではなく、それをどのように“進化”させるかが、これからの経営の本質と言えるでしょう。
未来予報株式会社では、会社の未来像が見えない中小企業の方々に向けて、自社の未来像を社員と共に描き直すセミナー・ワークショップを開催しています。
気になる方は以下から資料をダウンロードしてみてください。